 |
||||||||||

|
||||||||||
|
クルマは「所有」から「利用」に,EVで販売チャネルも多様化 消費者が“走る喜び”や“生活の足”をライフスタイルや価値観で選択する時代に
[2010/02/10]
少子高齢化や価値観の多様化に加えて,長引く不況,将来の生活不安や経済格差などを背景にした「クルマ離れ」が露呈して久しい。自動車メーカー各社は,縮小する国内市場のテコ入れを模索する一方,中国やインドなど新興国市場での事業拡大に本腰を入れ始めている。とはいえ,我々が現代社会で生活する上で,移動手段(モビリティ)は必要不可欠である。つまり,クルマへのニーズが無くなったわけではない。こうした背景から,都市部や若年層を中心にクルマは「所有」にこだわらず「利用」するモノへと変わりつつある。また,従来のクルマと構造が大きく異なる電気自動車(EV)の台頭と共に,販売チャネルもメーカー系列の販売店から多様化する流れが加速しはじめた。 若年層の60パーセントがクルマは「単なる移動手段」と回答 ソニー損保が今年1月中旬に新成人1000人に対して行った「新成人のカーライフ意識調査」では,現代の若年層がクルマに対してどのような価値観を持っているかについて興味深い結果が出ている。特に,「あなたにとっての車はどのような価値があるか」という設問に対する回答では,都市部と地方のいずれでも約60パーセントの回答者がクルマは「単なる移動手段としての道具」と答えたのだ(図1)。一方で,自動車メーカーの首脳や企画担当者の方々がたびたび口にする「走る喜び」(この調査の選択肢では「運転することそのものを楽しむもの」が相当)と回答したのは,都市部で15パーセント,地方でも17パーセントと比較的少数派であることがわかる。 このような傾向は,実際に日本の自動車市場で起こっている現象とも符合している。例えば,地方ではクルマがないと生活が困難であるため,「生活の足」として軽自動車や小型車がよく売れている。また,クルマ離れが顕著な都市部では駐車場など維持費が高くつくマイカーの保有を手控えて,自転車,電車やバスとともに必要に応じてレンタカーやカーシェアリングを使う消費者が増えている。 少子高齢化もクルマの所有から利用への変化を後押しする。高齢者が身体の衰えや安全のためにクルマを自ら運転しなくなれば,公共交通機関や自転車,家族など他の誰かが運転するクルマに乗る人が増える。必然的に,維持費がかかるマイカーの所有を続ける人口や世帯の数は減少することになる。自転車や車イスをタクシーで運ぶサービスを提供している富士タクシー(愛媛県松山市)の代表取締役・加藤忠彦氏は「長期的には日本は高齢化していくのが分かっている。人々はマイカーを運転しなくなる」と指摘する。
構造が簡単なEVは量販店の“家電製品”に 必ずしも所有にこだわらない様々な形態へとクルマの利用が多様化する流れは,自動車メーカーとその系列販売店がクルマの流通チャネルの中心であった業界構造を大きく変える可能性が高い。実際,自動車流通チャネルの多様化は,残価設定型ローンによる自動車の販売,中古車販売大手のガリバーインターナショナルが手がける中古車賃貸サービス,インターネットによる中古車の販売など多様化が始まっている。そして,その流れを加速させる大きな要因の一つが,従来のクルマとは構造が大きく異なるEVの台頭だ。 これまでの自動車製造業は,2万個とも3万個とも言われる部品を組み立てる,すり合わせの代表的な参入障壁の高い産業であった。ところが,EVは部品点数が内燃機関ベースの従来車両の10分の1以下といわれる。極論すれば,車台にモーターと電池,インバータなどの電気系の制御装置を組み付けるだけでできあがるのだ。ある電力会社の企画担当者は「家電量販店とも付き合いがあり,EVは家電製品になりつつあると認識している。(EVは)構造もそれほど複雑ではないので,量販店もEVを売るようになるのではないか」という。 ベンチャー系EVが示唆する自動車流通チャネルの多様化
このほかにもEV/PHVの普及に向けた課題として,「蓄電池の低コスト化」,「充電インフラの整備」,「人々の意識の変化」の視点でさまざまな議論がある。テクノアソシエーツではこれら課題の視点から,業界関係者のコメント,各種データを踏まえ,今後のEV普及と周辺ビジネスの実現性を検証し,調査分析レポート「EVの普及と社会システムの変貌に潜む20の仮説」としてまとめた。
(大場淳一=テクノアソシエーツ)
|
 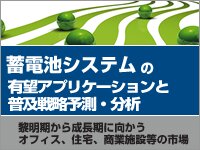 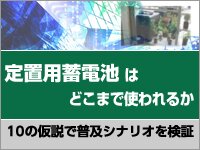   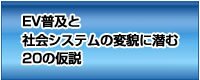 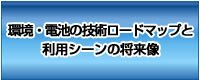 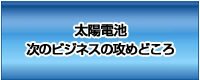 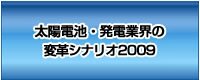 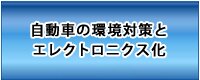  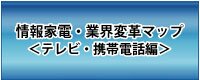 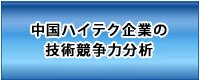 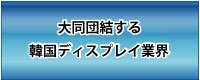 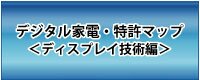 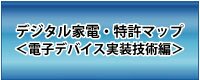 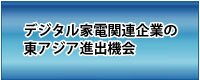 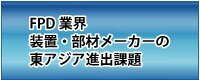 |
|||||||||
|
| 産業イノベーションHOME | 電子産業・成長戦略フォーラム |
Copyright (c) 2005-2011 TechnoAssociates, Inc. All rights reserved. |
||||||||||



